エディオンピースウイング広島
SPECIAL INTERVIEW

エディオンピースウイング広島 概要
■所在地:広島県広島市中区
■敷地面積:49,914.04㎡
■建築面積:26,056.26㎡
■延床面積:65,878.00㎡
■階数 :地上7階
■構造 :RC造・一部SRC造・S造
■発注者 :広島市
■設計者 :東畑建築事務所・環境デザイン研究所・大成建設・復建調査設計JV
■監理者 :東畑建築事務所・あい設計・シーケィ・テックJV
■施工者 :大成建設・フジタ・広成建設JV
■運営者(指定管理者):サンフレッチェ広島
2024 年 2 月、広島市中心部に誕生したサッカースタジアム(約 28,500 席)。発注者は広島市。広島の人々とまちに活力を与える新たな交流拠点として、また、サンフレッチェ広島の新たな本拠地として整備されました。「平和の翼」を造形化した軽やかな白い大屋根が特徴で、サッカー以外のイベントも開催され、試合のない日でも賑わいをみせています。現在、指定管理者として運営を担当しているサンフレッチェ広島の森重圭史氏に、新スタジアムの効果や今後の展望などを伺いました。(2024年 12 月収録)

森重 圭史 氏/サンフレッチェ広島 事業本部 スタジアムビジネス部 部長
interviewer:
川野 久雄/大成建設 設計本部 設計プロジェクト・マネジメント部 部長

写真右:川野 久雄/大成建設 設計本部 設計プロジェクト・マネジメント部 部長
川野:まずは今シーズンを振り返って、新スタジアムの効果や反響を伺わせてください。計画当初、本事業が目指す3本柱として「観客体験の向上」「多目的利用」「地域との融合」を掲げましたが、実際に運営されてみていかがでしたか?
森重氏:おかげさまで 2 月の開業直後から、各方面より非常に良好な反響をいただき、今季の好成績やサポーターの増加は、間違いなく新スタジアムの効果と言えると思います。一番の評価は観客席の視界の良さやピッチとの距離感、また演出面など、観戦のクオリティの高さですが、当クラブはもちろん、周辺含めた経済効果の大きさも実感しています。8月には、スタジアムに隣接する約2.3haの芝生広場と商業施設「HiroPa」が開業しました。これにより、「ひろしまスタジアムパーク」は全面開業を迎え、広島市や関係者が思い描いていた「世代や国をこえて、人々が集い、楽しみ、歓喜し、憩う、まちなかスタジアム」の姿が、いよいよ現実のものとなりつつあります。その中で、サンフレッチェ広島も広島という都市ブランドの向上に大きく貢献していると感じています。
川野:先日、J1リーグ戦のホーム最終戦セレモニーで、仙田信吾相談役(前代表取締役社長)が新スタジアムの効果によって「サンフレッチェ広島は、もうJリーグのイチ地方クラブではありません。Jリーグを引っ張っていく存在になっていきます」と仰っていたのが印象的でした。
森重氏:数字的には、J1 リーグ戦での観客動員数(1 試合平均)は前年度の 1 万 6,128 人から、 2 万 5,609 人へと大幅にアップしました。これはリーグ 3 番目で、クラブの営業収入も前年度から 1.7~1.8 倍の 70~80 億円になる見込みです。また、周辺の商業施設や飲食施設にサポ ーターの皆様が立ち寄っていただくことで、周辺地域の「集客」にも貢献できており、それに誘発される新たな雇用やビジネス機会なども考慮すると年間で数百億円規模の経済効果が生じていると推測されています。
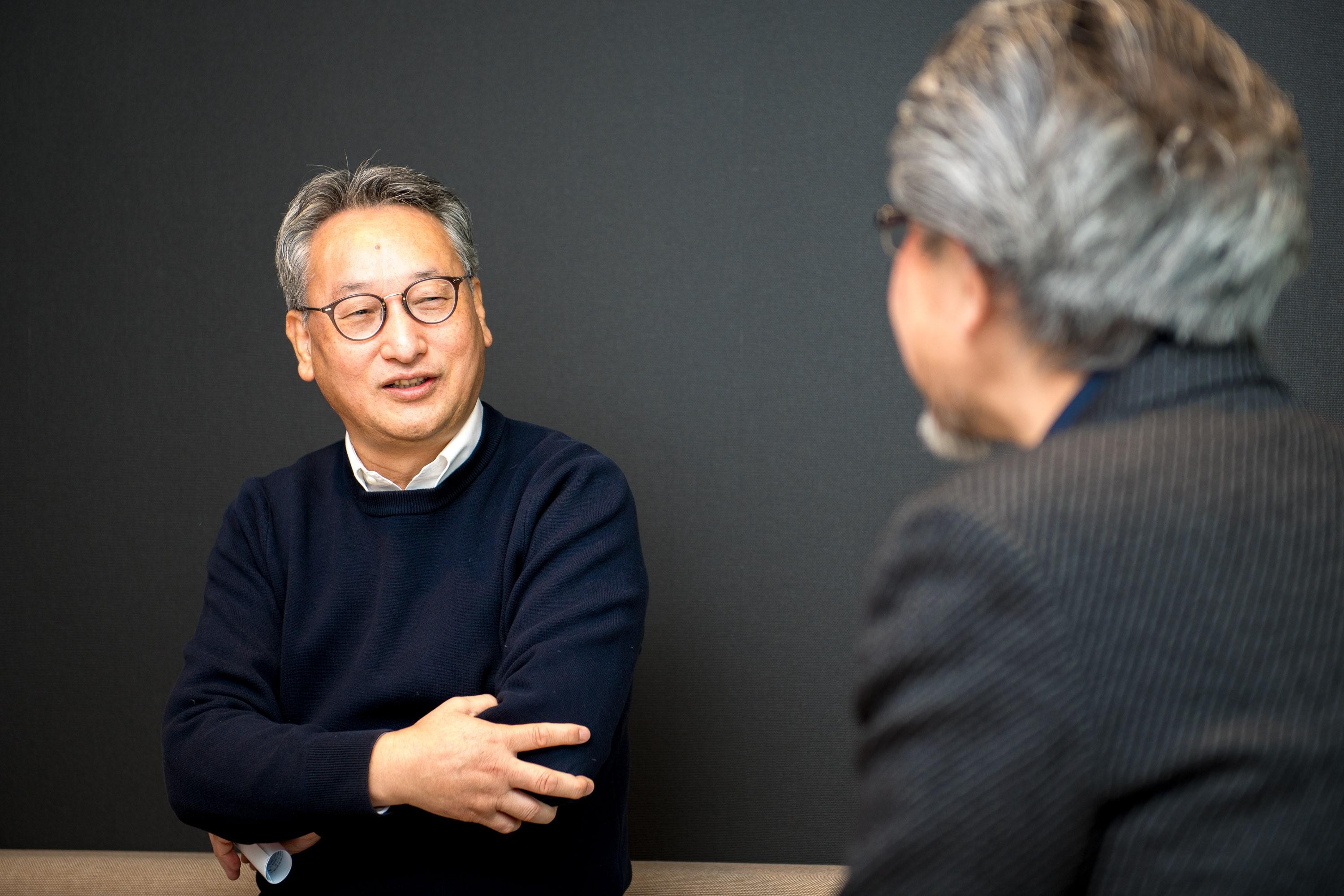
川野:それは実際にサポーターが増えたということでしょうか?
森重氏:これまで観客はコアなサッカーファンがほとんどでしたが、今年は家族3世代で来場される方や女性が目立つようになり、ファン層が拡大しました。これはクラブにとって非常に大きな効果です。また、平日の動員数が劇的に増え、2024シーズンのリーグ戦で平日ゲームの3試合中2試合が完売、2万人以上が来場し、年間指定席は販売当日に完売しました。
川野:近年、サッカーだけでなく、野球やバスケットボールなど、全国的に新スタジアムが次々と開業し、同様にファン層の拡大やまちの活性化を図っていますが、成功の鍵はどこにあると思いますか?
森重氏:広島のファン層拡大には、まちなかスタジアムという利点が効いています。足を運びやすいということだけでなく、その賑わいの波及効果が非常に大きい。試合のある日は、クラブのカラーである紫のアイテムを身に纏ったサポーターがまちに溢れ、スタジアム周辺は紫一色に染まります。サッカーに興味をもったり、自分も行ってみたいと思う方が多くいらっしゃったということだと思います。そして広島では28,500席という規模がジャストフィットでしたね。キャパシティや組み合わせる機能については、その都市の人口や周辺環境など、状況にあわせてそれぞれの最適解があり、さらに大切なのは運営であると考えています。
川野:サポーターからの声はいかがですか?
森重氏:冒頭で申し上げた通り、非常に好評なのが、観客席がピッチに近く、試合時の臨場感が高まったことですね。以前のホームスタジアムは陸上競技施設だったのでピッチの周囲にトラックが引かれ、結構距離がありました。それがなくなったことで没入感が飛躍的にアップしました。また、最新の照明・音響システムが導入されたおかげで、エンタテイメント要素が格段に向上しました。特に夏のナイトゲームでの照明を使った演出が女性に好評だったようです。また、移動ストレスが少ないことも大きく評価されていますね。さまざまな公共交通機関を利用してアクセスが可能で、到着してから退場するまでの一連の流れもスムーズです。
川野:スタジアム内の回遊性に加え、2階レベルに設けたペデストリアンデッキで周辺環境とつながり、まちの回遊性も向上させています。しかもデッキやフィールドビューテラスは、試合のない日も開放されており、これは本当に素晴らしいことです。選手やスタッフからのスタジアムに対する評価はいかがですか?
森重氏:やはり選手からも、サポーターとの距離感は評価が高く、パフォーマンスに良い影響を与えているようです。新スタジアムの存在が、非常に大きなモチベーションとなり、それが今季の成績にも反映され、クラブのブランド価値を大きく高めたことはまちがいありません。メディア露出の機会も増え、ホームゲームを観戦することが「魅力的な体験」として広く認識され、スポンサーシップ契約やクラブの経営面にもポジティブな影響を与えています。今後の課題としては、天然芝のメンテナンスですね。生き物なので本当に難しいですが、引き続き、選手がプレーしやすい環境の実現に取り組んでいきます。

川野:バルコニーやテラスには、多様なソファー席やテーブル席を設けたほか、ミニテーブルが付いたペア席、コンセント付きのカウンター席など、座席をバリエーション豊富に用意したことも功を奏したのではないでしょうか?
森重氏:42席種はJリーグ最多です。試合中、「次はあの席で観戦してみたい」と思われる方も多く、リピーターの獲得にもつながっているようです。中学校や高校のサッカー大会の試合時は、家族などのグループ利用にも重宝されていますね。そのほか高評価をいただいているのが、先進的なバリアフリー設備です。車いす席の多さや、新設スタジアムでの常設は国内初となるセンサリールーム(聴覚・視覚など感覚過敏の症状がある人やその家族が安心して過ごせる部屋)、ヒアリングループ(難聴者の聞こえを支援する設備)など、より多くの方がサッカー観戦を楽しめる環境が整っています。
川野:スタンドの一部にロールバックチェア(移動観覧席)を採用し、座席を収納すれば平場のスペースとしてイベントなどに活用できます。私はこれまで数多くの競技施設を手がけてきましたが、スタジアムはもっと「変容する場」であってほしいと思っています。今回は敷地のポテンシャルが高いことから、幅広い利活用を念頭において設計しました。
森重氏:我々は今年から、サッカーのクラブチームであるだけでなく、スタジアムの管理•運営者としての1歩を踏み出したわけですが、「365日にぎわうスタジアム」の実現に向けて、スタジアムを活用したイベントの企画・開催はもちろん、フィールドやスタンド、会議室の貸し出しにも取り組みました。その際のさまざまなシーンで、利用者目線での設計に助けられています。ユニークなイベントとしては、6月の「日本肝胆膵外科学会」の学術集会。大型ビジョンに研究成果が映し出され、それをスタンドから見るというスタジアムの使い方です。コンコースでは簡単な懇親会も行われました。11月には広島の伝統芸能「神楽」が披露されるなど、県内外の多くの方々に親しまれる場になりつつあります。
川野:それは今までにない光景ですね。もう1つ、設計の時に考えていたことは、広島のこの場所にふさわしい「シンボル性」です。戦後復興のシンボルである基町住宅群に近接し、平和記念公園からは、旧太田川(本川)越し、かつ原爆ドームの背後に見えることになるので、どのような造形であるべきか、市や設計JVなど関係者のなかでも議論を重ねました。軽やかな白い屋根「ピースウイング(平和の翼)」は、まちに開かれ、人々が安心して集うことができる、国際平和文化都市・広島の願いを表現したものです。
森重氏:広島の川や山といった自然豊かな風景の中での佇まいがいいですよね。こんなに四季で表情が違うスタジアムは他にないと思います。朝、出社前に時間の余裕がある時は、よく路面電車を途中下車して、スタジアムの写真を撮っています。
川野:試合終了後、帰路についた皆さんが、旧太田川に架かる橋の上から次々と写真を撮っている様子を見て、私も非常に嬉しくなりました。
森重氏:ライトアップ時の水面に映る姿がまた綺麗ですよね。当初はナイトゲームがある時だけだったのですが、今は毎日22時までライトアップしています。コーナー部の大きな開口部から柔らかい光が漏れ出し、夜空に翼が浮かび上がるような光景は、安心感と明日への活力を与えてくれます。

川野:週末などは、サッカー観戦に熱狂する人たちがいる一方で、芝生ひろばで遊んだり、旧太田川の河川敷でキャンプやバーベキューを楽しむ人たちの姿もあって、皆さん思い思いに過ごしている風景がいいなと思いました。
森重氏:そうですね、私も平日の夕方など、近所に住む小学生たちが、下校途中にフィールドビューテラスで宿題をする姿を見かけることがあり、本当にいい風景ができたなと思います。これまで広島の中心部には、意外と「憩える場」が少なかったのかも知れません。前職でエディオンの店舗開発に携わっていた時、東京・二子玉川の蔦屋家電など、家電だけでなく「居心地」を売る店づくりを行いました。運営チームには、そのほかいろんな分野で経験を積んだ、サッカー好きのスタッフが集まっています。このスタジアムも、単なる競技施設を超えて、地域の文化やスポーツ活動を促進する「居場所」にしていきたいと考えています。
川野:スタジアム1階の「広島サッカーミュージアム」でも展示されていますが、建築家の丹下健三氏は1950年に発表した「広島平和公園計画」で、平和の軸線の北端となるこのエリアにスタジアムをつくる構想をしていたんですよね。祈りの聖地である平和記念公園の「静」の場と、スポーツを楽しんだり、多くの人が集って平和を謳歌する「動」の場の双方がまちなかにあるという考えだったのではないでしょうか?
森重氏:同感です。日常の中にスポーツがあることはとても重要だと思っていますが、特に広島は戦後復興の中でスポーツが生活と密接に関わり、広島の人の生きる力になってきました。2009年に開業したMAZDA Zoom-Zoomスタジアムの盛り上がりもあり、近年より一層、スポーツ文化の高まりを感じます。丹下健三さんをはじめ、これまで広島のまちをつくり上げてきた皆様の想いを引き継ぎ、国際平和文化都市に相応しいこのスタジアムが、広島の新たなシンボルとなるよう運営していければと思っています。
森重圭史氏プロフィール
1987年家電量販店ダイイチ(現エディオン)に入社。 2000年には本社へ配属となり、商品部長、営業部エリア長を務め、蔦屋家電(二子玉川・広島)のプロジェクトリーダーやロボットプログラミングスクール事業に携わる。 2023年4月からサンフレッチェ広島に所属。
川野久雄プロフィール
1991年大成建設 入社。 以降、札幌ドーム、等々力陸上競技場メインスタンド、国立競技場、エディオンピースウイング広島などのスポーツ施設の設計をメインに行っている。
