プロジェクトの進め方

プロジェクトの進め方
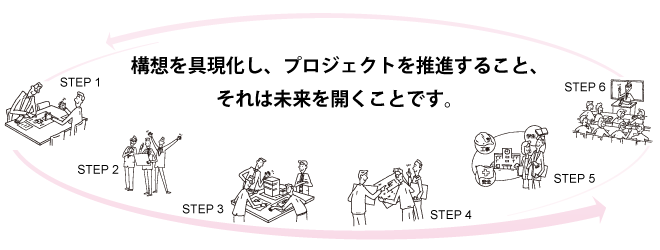
STEP1:客観的な現状把握
- 目的・概要・条件の確認
- プロジェクトの目的・意義・制約条件を確認、意向要望を洗い出します。
- 保有財産の評価、潜在能力の明確化
- 学内データを元に校地や施設の現況、使い勝手、規模、法的要件を把握、評価します。

STEP2:課題の共有と方針の策定
- ニーズ(与条件)、問題点の顕在化
- 「経営・事業」、「教学・研究」、「施設・環境」の3つの視点から、与条件を整理。
学内での共通認識を高める材料を作成します。
- 解決策のリストアップ
- 最適解を導き出すために考えうる解決策をすべてご提示します。キャンパス・プログラム技術

- キャンパス・プログラム技術
- ※詳しくは、「キャンバス・プログラム計画技術」をご覧ください。
STEP3:計画の立案と合意形成
- プロジェクトテーマの抽出、決定
- もっともふさわしい、一緒に目指すべきテーマや具体的な施策を提示します。
- 成果の予測と共有
- テーマを基に、様々な空間や要素技術を駆使して、実現されるキャンパスを可視化。夢のかたちを学内で共有するお手伝いをします。

- 保存・再生技術
- ICT化
STEP4:多様な可能性を具体化する設計
- テーマの具現化
- 実際のものづくりが行えるための設計図を、利用者の目線できめ細やかに配慮しながら作成していきます。
- 成果物のイメージ共有
- 先進の技術を活用しながら、設計図が実体化された際のイメージを共有しながらプロジェクトを推進していきます。

- VR(バーチャル・リアリティ)
- BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)(PDF)
- 免震技術「ハイブリッドTASS構法」
- 耐震補強技術「T-Grid」
- 耐震天井「T-Ceiling」
STEP5:学内外と共存する気配りの施工
- 安全でスケジュール通りの具現化
- 最新の建設技術を投入し、学校運営を中断することなく、かつ絶対的な安全を確保しながら、工事を行います。
- 近隣との関係を保持する施工
- 竣工後も、学校と良好な関係がより深く続くように、近隣へも最大限配慮した工事を行います。
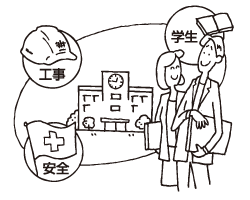
- 騒音・振動シミュレーション
- 体験型ワークショップ
STEP6:新たなフェーズに備える
- 使いながらのカスタマイズ
- 竣工後、お使いいただく中で気づいた点や、データ取集の結果明らかになる改善点を共有し、さらなる使いやすいキャンパスを目指します。
- 満足度調査
- 竣工後も学校側との関係を絶やすことなく、お使いいただいている上での評価を集積していきます。
- パートナーシップ
- 24時間カスタマーサポートやCSセンターの配置など、運用段階においても良きパートナーとしてサポートします。
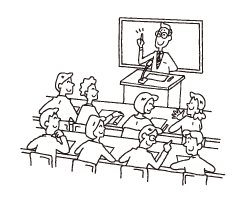
- 長期修繕計画
- CAFM
